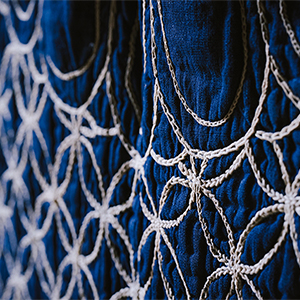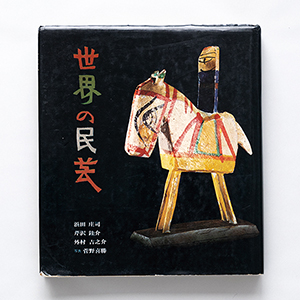朝日新聞社催事サイト利用規約
「朝日新聞社催事サイト利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社朝日新聞社及び催事の共同主催者(以下、総称して「当社」といいます)が主催する展覧会等の催事のウェブサイト(以下、総称して「本サイト」といいます)の利用規約です。本サイトの閲覧・利用を行う利用者は、本規約及び本規約下の「アクセスデータの利用について」「推奨環境・プラグイン・リンク等について」の内容に同意の上、ご利用いただくものとします。
第1条(適用)
本規約が適用される「利用者」には、本サイトを利用する方全てが含まれます。
第2条(外部コンテンツ)
当社以外の事業者が管理運営するリンク先のホームページ等で利用可能となっているコンテンツ及び当社以外の事業者が管理運営するソーシャルネットワーキングサービス(Facebook、Twitter等)の機能または動画埋め込み機能を使って本サイト内に表示するコンテンツ、本サイト外から引用、転載され本サイト内に表示されるコンテンツ(以下、総称して「外部コンテンツ」といいます)並びに外部コンテンツにおける広告、商品、サービスなどについて当社は責任を負いかねますので、利用者の判断及び責任においてご利用ください。
第3条(利用者の責任・費用)
1.利用者は、自己の責任で本サイトを利用するものとし、本サイトを利用した結果、損害や不利益を被ったとしても、利用者自身が責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰する場合はこの限りではありません。
2.本サイトの利用のために必要な通信料や、コンピューター・通信機器等に関する費用は、利用者の負担とします。
第4条(著作権)
本サイト及び本サイト内の全てのコンテンツに関する著作権その他の権利は、当社及び正当な著作権者に帰属します。利用者は、本サイトの内容について、当社の事前の書面による許可なく転載、複製、転用、転送、販売等の二次利用を行うことはできません。
第5条(免責事項)
1.当社は、本サイトの内容及び機能について、いかなる保証(その完全性、正確性、確実性、有用性、安全性、正常動作性、機能性を含みますが、これに限りません)も行いません。また、当社は、本サイトの内容及び機能を、編集、管理、削除等し、またはこれに必要な技術的な手段を利用者に提供する義務を負わないものとします。
2.利用者は、以下の事項を了承の上、本サイトを利用するものとします。
(1)本サイトの変更、中断、遅延、停止、終了または不具合が生じる場合があること
(2)第三者または他の利用者とのトラブルが生じた場合に、利用者の責任で対応すること
(3)本サイトを通じて第三者から取得した情報等もしくは第三者との取引等により生じたトラブルは利用者の責任で対応すること
(4)上記各号について、当社がその責を免れること
(5)本サイトに起因して発生した一切の損害((1)~(3)に関連して生じた損害を含みますがこれに限りません)について当社が責任を負わないこと(ただし、当社の責に帰する場合はこの限りではありません)
第6条(禁止事項)
利用者は、本サイトに関して、以下の行為を行わないものとします。
(1)本サイトのコンテンツ等一切を第三者へ提供・再配信する行為
(2)本サイトの正規機能によるものを除き、本サイトのコンテンツ等の複製(閲覧の際に端末上に一時的に発生する電子的蓄積は除く)、編集、加工、翻訳、翻案、出版、転載、頒布、放送、口述、展示、販売、公衆送信(送信可能化、インターネット上のウェブサイトやイントラネット等への掲載を含む)及び改変をするなど、当社及び第三者の権利を侵害する一切の行為、あるいはこれらを行ったコンテンツ等一切を第三者へ提供・再配信する行為
(3)本サイトを、営利を目的として利用する行為、またはその準備を目的とした行為
(4)データマイニング、ロボット等によるデータ収集・抽出ツールを使用する行為
(5)本サイトの全部もしくは一部のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルする等の行為
(6)第三者または当社の財産、名誉・信用・肖像・プライバシー・パブリシティーに係る権利、著作権・特許権・商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害を助長する行為
(7)上記各号に定めるほか、法令に違反する行為またはそれを助長するおそれがある行為
(8)本サイトの運営または他の利用者による本サイトの利用を妨害する行為
(9)その他、当社が合理的な理由に基づき不適当と判断する行為
第7条(規約・サービスの変更等)
1.当社は、利用者の事前の同意を得ることなく、予告なしにいつでも本規約を変更できるものとします。変更後の本規約は、当社が特に定める場合を除き、本サイト上に表示された時点から効力を生じます。
2.本規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効または実施できないと判断された場合も、当該規定以外の各規定は、いずれも引き続き有効とします。
3.当社は、利用者の事前の同意を得ることなく、予告なしにいつでも本サイトの全部または一部を変更し、本サイトの提供を中断または終了できるものとします。
第8条(準拠法、裁判管轄)
1.本規約は日本国法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。
2.利用者と当社の間で本規約及び本サイトに関する紛争が生じた場合、両者で誠意をもって協議をするものとしますが、それでも解決しない場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年1月18日 施行